「トラック簿」遠隔受付と予約機能の活用で成果、全国拠点に導入し物流2024年問題への対応とホワイト物流推進へ 株式会社コクヨロジテム神奈川配送センター

.jpg)
- 会社名
- 株式会社コクヨロジテム
- 業種
- 物流
- 従業員数
- 322名 (2025年 8月1日現在)
- 所在地
- 神奈川県海老名市中新田(神奈川配送センター)
- URL
- https://www.kokuyo-logitem.co.jp/
株式会社コクヨロジテム 神奈川配送センターでは、受付でのトラックの滞留や待機時間が課題になっていた。また全社的な物流2024年問題への対応・「ホワイト物流」推進に向け、正確な現状把握も求められた。そこでトラック簿を利用して遠隔受付を導入。センター移転後は予約機能も導入し、待機時間削減に成果を挙げている。また、神奈川配送センターをモデルセンターとし、全国の物流センターにもトラック簿を導入し、全社的な改善を進めている。
株式会社コクヨロジテムは、コクヨのオフィス家具事業において、主にオフィス、学校などの働く場、学ぶ場をつくる「空間構築事業」、保管、荷役、輸配送などの「ロジスティクス事業」を行う企業です。同社神奈川配送センターは、エンドユーザーへ向けた出荷の拠点として神奈川県・山梨県などを管轄し、季節によって変動はありますが、1日あたり10トン車3〜4台程度の荷受けと、配送車両(2〜4トン車)10〜15台程度への積み込みを行っています。
同センターでは、以前入居していたマルチテナント型物流施設において、受付でのトラック滞留や、受付後の待機が課題になっていました。また、全社的に物流2024年問題への対応を進め、国土交通省が提唱する「ホワイト物流」推進運動に賛同する中で、効率化・トラックドライバーの長時間労働の是正に向けて、待機時間の正確な把握の必要性を感じていました。
このような状況からトラック簿を導入し、遠隔受付を活用して滞留を抑制。さらにその後、新しい物流センターへの移転を機に予約機能も導入しました。現在は、同社の全国の物流センターでトラック簿が活用されています。
当初の課題と現在までの成果をうかがいました。
武田 貴之様 お納め本部 副本部長 兼 運用推進部 部長
岸本 篤様 お納め本部 運用推進部 運用課 主任
原 和高様 お納め本部 首都圏ブロック 神奈川配送センター 所長 管理課長 兼 配送課長
柞原 杏香様 経営統括本部 経営管理部 人事グループ(品川オフィス駐在)
(以下、敬称略)
トラック簿を選んだ理由
(1)多層階テナントでの受付前のトラック滞留や待機時間が課題になっていた
(2)物流2024年問題への対応や「ホワイト物流」推進に取り組むために、現状把握が必須だった
(3)カスタマイズ性の高い料金プランが事業の特性に適していた
受付の滞留解消と、物流2024年問題への対応・ホワイト物流推進へ向けた現状把握のために導入
——神奈川配送センター様では、移転前の拠点でトラック簿を導入されたそうですが、当時どのような課題があったのでしょうか。
柞原:神奈川配送センターは、お客様に直接商品をお届けする拠点として、東京都の一部、神奈川県と山梨県全域、静岡県の一部を管轄しています。取り扱っているのは、コクヨのデスクや椅子、ロッカーなどのオフィス家具が中心です。以前はマルチテナント型物流センターの4階に入居していました。
原:当時、納品のトラックが到着するとランプウェイで4階まで上がってもらい、受付をした後1階へ戻り待機場で待っていただき、バース側の準備ができたらトラックを電話で呼び出すという流れでした。ドライバーさんの負担も大きかったですし、ときには4階のテナント前に受付をするトラックが滞留してしまい、他のテナントさんのご迷惑となってしまうこともありました。加えて、トラックごとの待機時間も把握できていませんでした。
武田:当社は2019年ごろから「物流2024年問題」への対応に取り組み始め、国土交通省の「ホワイト物流」推進運動への賛同を表明し、物流の効率化やドライバーさんの負担軽減に積極的に取り組むこととしました。改善するには、まず現状を把握し課題を洗い出さなくてはなりません。現場の課題と、企業としての物流効率化の取り組みの両面から、システム化が求められていたわけです。
お納め本部 副本部長 兼 運用推進部 部長 武田様
——トラック簿を選んでいただいたポイントはどんなところでしたか?
武田:当社が扱うオフィス家具は時期による物量の差が大きく、また全国のセンターで地域ごとに特色が異なります。トラック簿なら月ごとにプランを見直したり、必要な機能をオプションで追加したりできるなど、カスタマイズしやすい点が当社の業務形態に適していました。
配送会社さんと事前調整の上で予約時間帯を指定し、スムーズな運用を実現
——トラック簿導入後は、業務の流れはどのように変わったのですか
岸本:移転前の物流センターで4年ほど前にトラック簿を導入し、その時は遠隔受付の機能を活用しました。到着したドライバーさんに、4階まで上がらずに1階の待機場から遠隔で受付をしてもらい、バースの方で準備ができたらトラック簿の通知機能で呼び出して上がってきてもらう、という使い方です。受付だけのためにドライバーさんにわざわざ上がってきてもらう必要もなくなり、受付前のトラック滞留も回避できるようになりました。

操作の様子
——移転後はどのような流れでお使いですか?
原:現在の物流センターへ移動する際には予約機能も導入しました。まず、出荷元の倉庫から神奈川配送センターへ荷物を積んでくるトラックの情報が前日までに届くので、それを元に神奈川配送センターのスタッフが各トラックの来場予約枠を割り振ります。次に、弊社内で使用しているAccessのシステム経由で、来場予約枠の情報を配送会社さんにFaxで連絡します。配送会社さんの方で問題がなければ予約を確定し、調整が必要なら配送会社さんと神奈川配送センターのスタッフが相談の上、予約を組み直します。
最終的に予約が確定したらトラック簿に入力し、その情報が担当するドライバーさんのスマホアプリに届く、という流れです。当日ドライバーさんが物流センター敷地内に到着したら、アプリから遠隔で受付をしてもらい、物流センターから呼び出し通知が届いたら指定のバースに接車していただいています。
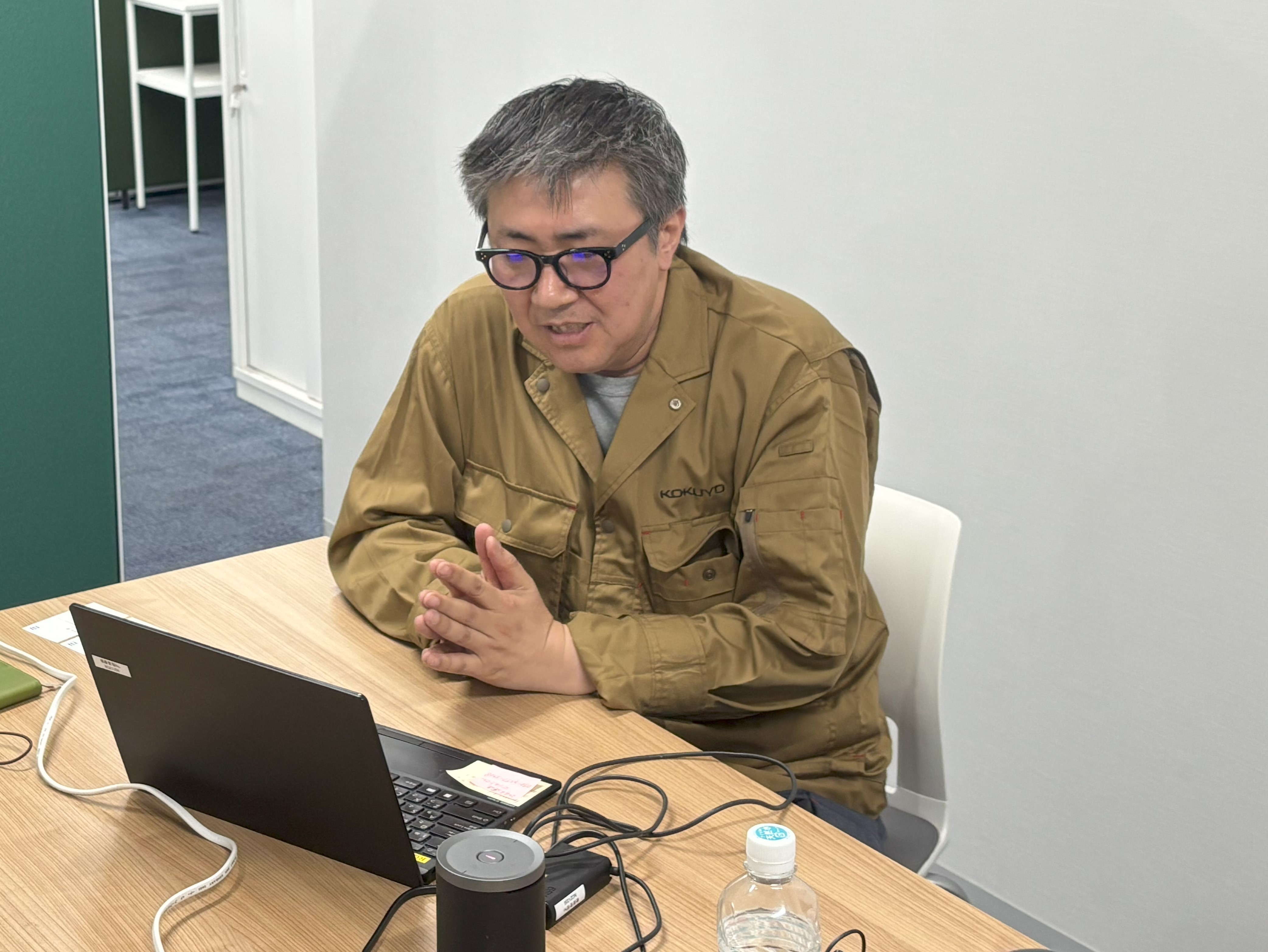
お納め本部 首都圏ブロック 神奈川配送センター 所長 管理課長 兼 配送課長 原様
——予約制にしているのは入荷のトラックのみですか?
原:どの時間帯にどの物流センターからの荷受けがあるのかが事前にわかるので、物流センター内での作業工程が組みやすくなりました。それと、ドライバーさんに受付へ来てもらう必要がなくなり、現場側もタブレットの呼び出しボタンを押すだけで連絡できるので、ドライバーさんも神奈川配送センタースタッフも負担軽減になっています。仕組みの導入当初はアプリ操作に戸惑うドライバーさんもいらっしゃいましたが、マニュアルの配布で解決できましたし、最近は他の企業さんでも同様のシステムの導入が進んでいることもあって、今は操作上の問題はほぼありません。
岸本:神奈川配送センターへの導入以降、当社の物流センターすべてにトラック簿を導入しました。使い方は各物流センターによって多少異なりますが、商品保管を担っている物流センターではすべて予約制を採用しており、予約枠の指定も神奈川配送センターと同じスタイルで行っています。
——もうひとつの課題であった物流2024年問題への対応・「ホワイト物流」の推進という面ではいかがですか?
武田:やはり現状を把握することで課題が明確になり、課題解決、改善の手が打てるようになりました。ドライバーさんの長時間労働を改善する物流2024年問題への対応、ホワイト物流推進の一助になっていると思います。また、全国の物流センターで、待機時間やバース使用状況のデータをもとに時間帯の割り振りを工夫するなど、物流センターが主体となった改善の取り組みが進んでいるのは非常に良い成果だと思います。さらに、各物流センターの取り組み事例を共有する場を岸本が中心になって作っています。物流センターによっては「バースの数が少ない」など、すぐには解決できない課題もある中で、「できることからやっていこう」という雰囲気を感じています。
ただ、退場ボタンの押し忘れなど、どうしても人為的なミスでデータが正確に取れないこともあります。もっと正確にデータを取ることが出来れば、さらに改善に繋げる道筋も見えてくるのではないかと思っています。この点は引き続きハコベルさんとともに改善を進めていくべき点だと考えています。
トラック簿の概要資料をダウンロードする
プライバシーポリシー をお読みの上、
同意して送信してください
