物流に革命をもたらすデジタルツインとは?メリットや活用方法を解説
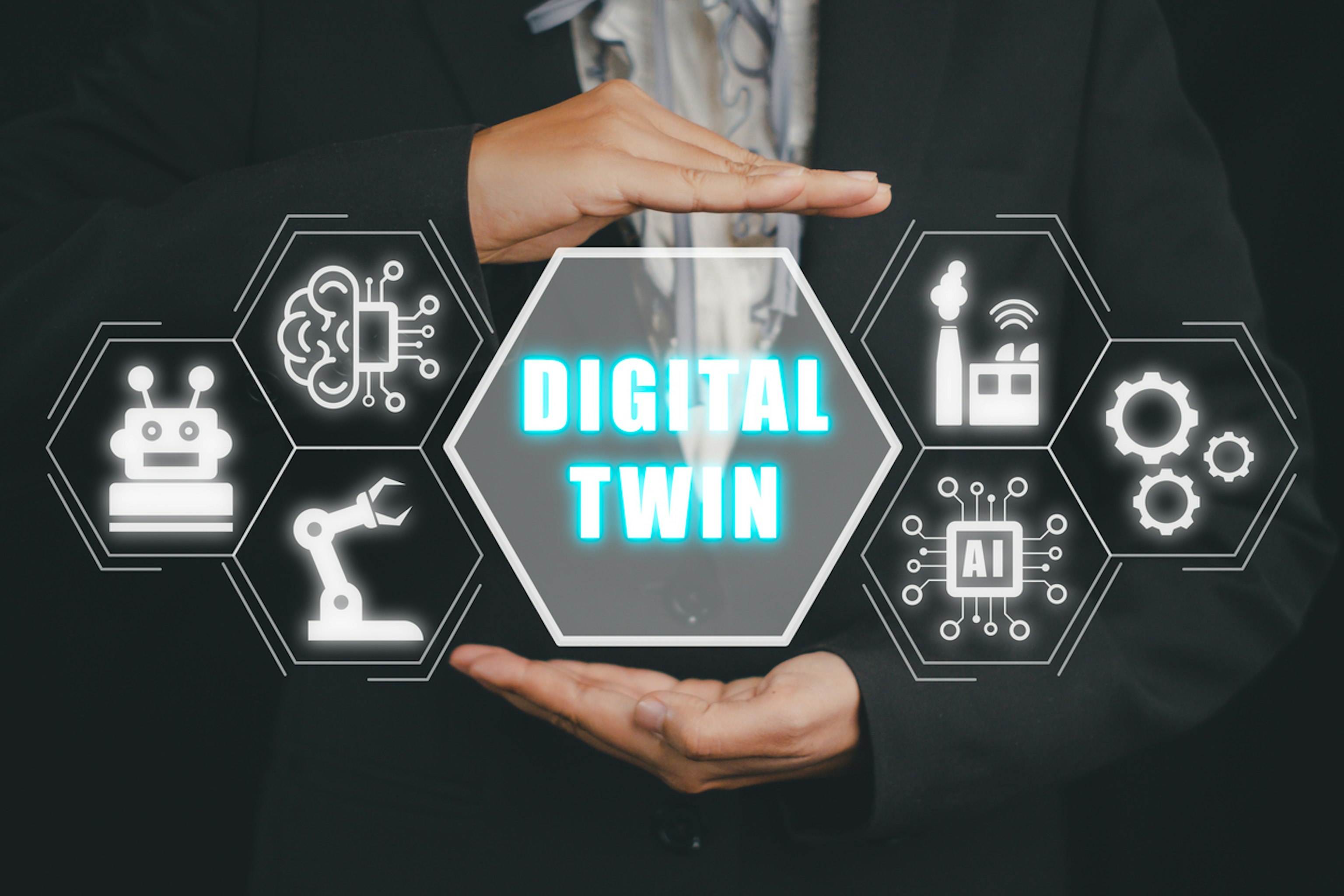
企業が抱えているさまざまな課題を解決し、競争力を高めていくためにはDX化への取り組みが効果的です。業務パフォーマンスを最大限に引き出し、新しい価値をもたらすことが可能となります。
企業がDX化に取り組む場合、重要な技術の1つとなるのがデジタルツインです。デジタルツインとは現実の世界をデジタルで作った仮想の世界に再現することで、さまざまな課題の解決に役立てられます。物流業界にデジタルツインを導入すれば、業務の効率化やコストの削減、作業員の安全性確保など多くのメリットが期待できるでしょう。
本記事では、デジタルツインの基本的な概念、重要性、活用場面などについて詳しく解説します。
この記事でわかること
- デジタルツインの基礎知識
目次
1. デジタルツインとは
デジタルツイン(Digital Twin)とは、現実空間の物理的なオブジェクトやプロセスを仮想空間(デジタル上)に再現する技術です。「ツイン」は双子を意味しており、現実空間と仮想空間が瓜二つな状態になるため、デジタルツインという名称がつけられています。(※)
※出典:総務省,令和5年版 情報通信白書 第1部 第1節(2)デジタルツイン
デジタルツインの概要
.JPG)
デジタルツインでは、現実空間にある各種機器をインターネットに接続し、情報をコンピューターに吸い上げて仮想空間を作り出します。
現実空間で再現が難しい状況を仮想空間に作り出すことができるため、さまざまな予測をしたり耐性を確認したりすることが可能です。
「シミュレーション」「メタバース」「デジタルトリプレット」との違い
シミュレーションやメタバースなど、デジタルツインと似ている用語があり、混乱する方も多いでしょう。ここではデジタルツインと類似している用語について解説します。
シミュレーション(Simulation)
シミュレーションは、決められたデータから仮想空間を構築する手法です。基本的には取り込むデータがあらかじめ設定されており、変更しない限り同じ結果となります。
一方デジタルツインは、リアルタイムに変化するデータを取り込んで仮想空間に反映する方法です。データの変化に伴って結果が変動するので、現実に近い再現が可能となります。
メタバース(Metaverse)
メタバースは、デジタルツインと同じように仮想空間を作り出す概念です。ただしメタバースは現実空間に存在しているかどうかは問いません。
例えば、現実空間に存在しないアバター(仮想空間での分身)を使って他人とコミュニケーションをとるなど、疑似体験が目的です。一方デジタルツインは実在しているものを忠実に再現し、分析や予測を目的としています。
デジタルトリプレット(Digital Triplet)
デジタルトリプレットは、デジタルツインに「経験知やノウハウ」などの人に依存する要素を組み込んだものです。トリプレットとは三つ子を意味し、「物理世界」「サイバー世界」「知的活動世界」を表しています。
例えば、現場の技術者の判断や知識を形式知化したり、製品ライフサイクル全体において技術者の問題解決や価値創造を支援したりすることが可能です。(※)
※出典:総務省,日本の製造業の現場の強みを活かしながらデジタル化を実現するための「デジタル・トリプレット」,p6
2. デジタルツインに活用されている技術
.JPG)
デジタルツインでは、さまざまな技術を活用し仮想空間に現実空間を再現しています。
ここでは、デジタルツインに活用されている技術について解説します。
活用されている技術 | 説明 |
IoT(Internet of Things) | IoTは機器がインターネットとつながり、データ通信する技術です。 例えば物流の各機器に取り付けられているカメラやセンサーをインターネットに接続して、情報を収集するなどの活用方法があります。 |
AI(Artificial Intelligence) | AIは人工知能のことです。 収集した膨大なデータを元に学習し、分析したり予測したりします。 |
AR(Augmented Reality) | ARはデジタル情報を現実の世界に映し出す技術です。 収集して作成した仮想空間の3D情報を現実空間に表示し、存在するように見せることが可能となります。 |
VR(Virtual Reality) | VRは仮想現実を指しています。 コンピューターが作り出した仮想空間を現実のように体験することが可能です。 |
5G(第5世代移動通信システム) | 5Gは大容量で高速のモバイル通信システムです。 多数接続が可能で、通信遅延が発生しにくくなるのが特徴です。デジタルツインの通信手段として考えられています。 |
その他にも、収集した膨大なデータを保管、処理、分析するための「クラウドコンピューティング」、リアルタイムでデータを処理するための「エッジコンピューティング」など、多くの技術の融合によってデジタルツインは実現されています。
※関連記事:物流システムの全体像|覚えておきたい6大機能と主要システム
3. デジタルツインを物流に導入するメリット
物流業界にデジタルツインを導入することで、時間短縮やコスト削減、輸配送業務の最適化などが期待できるでしょう。ここでは、物流業界にデジタルツインを導入するメリットについて解説します。
業務効率の向上
デジタルツインは、倉庫や配送センターの在庫管理、車両の位置や稼働状況をリアルタイムに可視化できます。また、シミュレーションを通じて業務の効率化を支援することも可能です。これにより、無駄な業務やリソースの非効率的な使い方を削減し、作業フローの最適化を図れます。
.JPG)
例えば、現実空間で業務プロセスやレイアウト、人員配置などの変更を行った場合、想定外の問題が発生したり、対策に追加コストがかかったりする可能性が考えられるでしょう。
デジタルツインを導入すれば、仮想空間で結果をシミュレーションし、発生する問題や対策、効果などを事前に確かめることが可能となります。シミュレーションの結果がうまくいかなくても、仮想空間の中だけで済むため、現実の業務に影響が出ることはありません。
リアルタイム監視と安全性の保持
従来は、工場の生産現場で監視業務を実施する必要がありました。しかしデジタルツインを導入すれば、各種機器の情報を取得し、仮想空間に生産現場を再現できるため、遠隔でリアルタイムに設備監視ができます。また機械故障などを事前に予測することもできるため、安全性の確保も可能です。
パフォーマンスの最適化とコスト削減
デジタルツインを用いて、物流の各業務をリアルタイムにモニタリングすることが可能です。モニタリングによって最適なパフォーマンスが発揮できる条件を割り出し、業務の効率化やコスト削減に活かせます。
※関連記事:物流倉庫とは?概要や作業効率化の戦略、IT活用事例をご紹介!
顧客理解の向上
デジタルツインでは、物流システムの設計において実際の機器の動きや配送の流れなどを仮想空間に再現できます。顧客に提案する場合、システムがどのように動き、どのように機能するのかを視覚的に伝えることができるため、理解を得やすいでしょう。
また顧客の要望に合わせて仮想空間のシステムをカスタマイズすることもできるため、商談を有利に進めることが可能となります。
4. デジタルツインを物流に活用する方法
物流でデジタルツインを活用するためには、さまざまな情報をコンピューターに取り込む必要があります。倉庫内を対象とする場合は物流ラインの各機器、設備、人員などの情報であり、輸配送を対象とする場合は車両、物流施設、道路交通などの情報です。
ここでは、物流にデジタルツインを活用する具体例について解説します。
在庫管理の精度向上
RFIDやセンサーを使って倉庫内の在庫状態を取得することで、精度の高い管理業務を行うことが可能となります。RFID(Radio Frequency Identification)とは、非接触タグと呼ばれ、商品ごとに取り付けられている識別コードです。無線でデータの読み取りができ、正確な在庫管理が可能となります。
輸送ルートの最適化
在庫状況や気象条件、交通情報などをリアルタイムに取り込むことで、運送スケジュールや輸送経路の最適化が実現できます。輸送遅延を軽減したり、コストを削減したりすることが可能です。
予測保守・予防保全
物流機器や輸送車両などにセンサーを取り付けて情報を収集し、デジタルツインで分析すれば、事前に故障や部品の交換時期を予測することが可能です。予防保全に役立てることができるため、故障による使用不能期間を削減し、信頼性やサービスの向上につながります。
シミュレーションとトレーニング
デジタルツインでは、トレーニングのためのシミュレーション環境を構築することが可能です。倉庫作業員やドライバーのスキルを向上させるために、疑似的な体験を提供することができます。
5. まとめ
本記事では、デジタルツインの基本的な概念、重要性、活用場面などについて解説しました。
デジタルツインを活用して現実空間の状況を仮想空間に再現することで、業務の改善に役立てたり、設備監視や保全を遠隔で行ったり、トレーニングに利用したりすることが可能です。
デジタルツインの活用は、企業の競争力を高めていくためにも有効な手段と言えます。デジタルツインの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)





