ダブル連結トラックの導入メリットと注意点を解説!政府施策も紹介
.jpg?fit=crop&w=3072&fm=jpeg)
物流業界は、ドライバー不足や輸送コストの増加、環境負荷の軽減といったさまざまな課題に直面しています。これらの課題解決に有効な方法の1つが、ダブル連結トラックの導入です。
従来型トラックの約2倍の輸送効率を持つダブル連結トラックは、CO2排出量や物流コストの削減にも大きく貢献します。一方で、導入には高額なコストや運転者の育成、通行区間の制限といった課題もあります。
本記事では、ダブル連結トラックの基本概要、メリット、導入における課題、政府の取り組みについて解説します。
この記事でわかること
- ダブル連結トラックとは
- 上記普及に向けた取り組み
目次
1. ダブル連結トラックとは

ダブル連結トラックとは、大型トラックの後部にもう1つフルトレーラーを連結したトラックです。従来型トラックと比較すると、1台で大きな輸送効率を実現できるため、物流業界で注目されています。
ここでは、ダブル連結トラックの基本的な特徴やその構造について詳しく解説します。
従来型トラックとの違い
ダブル連結トラックと従来型トラックの違いは、積載量と全長です。
従来型トラックは全長12m以内が標準となっているのに対して、ダブル連結トラックは2019年の規制緩和で25mまで許可されました。(※)
この拡張により従来型トラックの約2倍の輸送能力を持つことになり、大型トラック2台分の荷物を1台で運べるのが大きな特徴です。
なお、ダブル連結トラックの運転には牽引免許が必要で、一定期間の運転経験が求められます。
※出典:国土交通省:長大トラックの通行について,p1
タイプ別分類
ダブル連結トラックには主に次の2種類があります。
分類 | 説明 |
センターダブル連結トラックの通行区アクスル式 | 軽量でコンパクトな構造が特徴。 トレーラー全体の安定性と走行性を高める設計。 |
ドーリー式 | 中間連結部分が自立可能で、連結を解除しても後方トレーラーが安定して駐車が可能。 |
規制緩和について
ダブル連結トラックは、2016年に国土交通省が「生産性革命プロジェクト」の一環として実証実験を開始し、2019年には新東名高速道路を中心に本格的な運用がスタートしました。その後、運行区間が全国の主要高速道路へ拡大され、2022年には運行可能区間が約6,330kmに達しました。(※)
この規制緩和は、深刻なドライバー不足への対応策とされています。これによって、より大規模な輸送が可能となり、長距離輸送での活用が進められています。
※参考:
国土交通省,トラック輸送の生産性革命 「ダブル連結トラック」の本格導入を本日よりスタート~特殊車両通行許可基準の車両長を25mまで緩和します~
国土交通省,ダブル連結トラックの通行区間の拡充について,p10
導入の目的と期待される効果
ダブル連結トラック導入の目的は、輸送効率の向上、人手不足の解消、環境負荷の低減です。
1台のダブル連結トラックで大型トラック2台分の荷物を運ぶことで、車両台数の削減が可能となります。
CO2排出量の削減も期待できるでしょう。物流コストの削減にもつながり、荷主企業に経済的な利点をもたらします。
2. ダブル連結トラック導入のメリット
ダブル連結トラックは、物流業界における課題を解決する手段として注目されています。
ここでは、主な3つのメリットについて解説します。
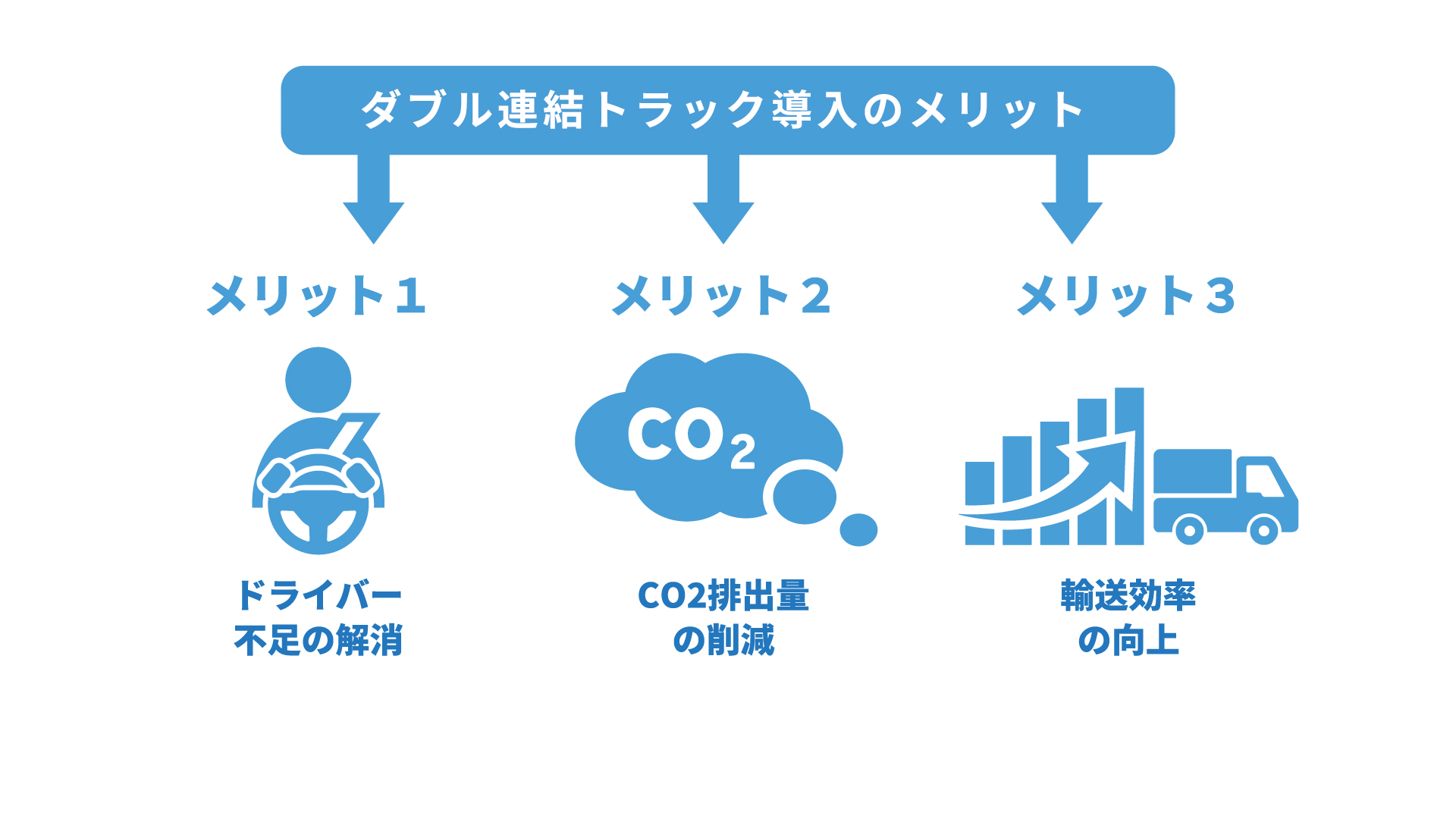
ドライバー不足の解消
ダブル連結トラックは、1台で従来の2台分の輸送が可能です。これにより、必要なドライバー数を削減でき、物流業界が抱える深刻な人手不足の解消が期待されています。
さらに中継輸送を活用すれば、長距離移動を複数のドライバーで分担でき、労働環境の改善にもつながります。
労働時間規制への対応
2024年から施行された労働時間規制では、トラックドライバーの時間外労働の上限が年間960時間に定められました。(※)
規制に対応するにあたり、ダブル連結トラックの利用は効率的な輸送手段と言えるでしょう。ドライバー1人で2台分の荷物を運べるため、運行回数を減らしつつ物流業務の継続が可能となります。
※出典:厚生労働省,トラック運転者の改善基準告示,改善基準告示改正のポイント
関連記事▶2024年問題によるドライバー不足の対策方法とは?原因や影響も解説
CO2排出量の削減
ダブル連結トラックは輸送効率が高いため、従来の大型トラックと比較してCO2排出量を大幅に削減できます。
国土交通省が実施した実験では、約4割の削減効果が確認されました。(※)
荷主企業がSDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けた取り組みを進める上でも重要なポイントとなります。
※出典:国土交通省,ダブル連結トラックについて,p10
関連記事▶グリーン物流とは?グリーン物流の推進方法を具体的に解説
輸送効率の向上
ダブル連結トラックは1回の輸送で運べる貨物量が大幅に増加するため、輸送回数の削減や物流ルートの効率化が可能です。
また共同輸送によって異なる荷主の荷物をまとめて運ぶことができ、業界全体の効率向上にもつながります。
積載率の向上
ダブル連結トラックは荷物の積載率を最大化するために設計されており、大型商品や大量輸送が求められる場面で特に効果を発揮します。これにより、空荷状態の走行が減り、効率的な輸送が可能になります。
共同輸送の推進
異なる荷主の貨物を1台のトラックに集約する共同輸送は、輸送効率を大幅に向上させます。
例えば複数企業が同じルートで荷物を輸送する場合、ダブル連結トラックを使用することで配送回数を削減可能です。この取り組みは、物流全体の最適化や業界全体のコスト削減、さらに環境負荷の低減にもつながります。
関連記事▶物流効率化に向けた政府の取り組みとは?荷主企業に求められることも解説
3. ダブル連結トラック導入における課題

ダブル連結トラックの導入には多くのメリットがある一方で、解決すべき課題も存在します。
ここでは、導入における主な課題について解説します。
導入コストの高さ
ダブル連結トラックの導入には高額な初期費用がかかります。
通常の大型トラック2台分以上の価格になることもあり、特に中小物流企業にとっては大きな負担となるでしょう。
運行中の維持費はエンジンが1台分で済むため軽減されるものの、導入コストの回収には長期間の安定的な運用が必要です。またトラック自体の特殊性により、専用整備や部品交換にかかる費用も加算される可能性があります。
運転者の確保と育成
ダブル連結トラックの運転には、特殊な技能と経験が必要です。
牽引免許に加えて一定期間の運転経験が求められるため、資格を持つドライバーの確保が難しいのが現状です。
具体的な条件は次の通りです。(※)
・大型自動車免許5年以上保有、および牽引免許5年以上保有
・直近5年以上の大型自動車運転業務に就いている
・2時間以上の訓練の受講、または優良運転手(最低12時間の訓練かつ直近3年間は無事故・無違反)に限り、牽引免許1年以上、大型免許3年以上、大型自動車運転業務に直近3年以上就いている
企業の中には、ダブル連結トラックの運転者育成プログラムを立ち上げる例も増えています。
※出典:国土交通省,ダブル連結トラックについて,p29
通行区間の制約
ダブル連結トラックは、すべての道路を自由に走行できるわけではありません。
一般道の一部や特定の高速道路区間でのみ運行が許可されているのが現状です。そのため運行計画が複雑化し、効率的な輸送が難しくなることがあるでしょう。
通行可能な道路が増えなければ、利用拡大は限られた地域にとどまる可能性もあります。
駐車スペースの不足
ダブル連結トラックは通常のトラックよりも大きいため、駐車スペースの確保が課題です。
特に高速道路のサービスエリアや物流拠点では専用の駐車マスが必要ですが、現状は十分な数が整備されていません。特に幹線道路沿いの休憩施設や物流拠点での駐車スペース不足は、今後の運用拡大を阻む要因となっています。
4. ダブル連結トラックの普及に向けた政府の取り組み
政府は、物流業界が直面する課題を解決し、ダブル連結トラックの普及を推進するため、さまざまな施策を推進しています。
ここでは、政府の取り組みについて解説します。
特車通行許可基準の緩和
ダブル連結トラックの導入は、深刻なドライバー不足を解決する重要な施策の1つです。
政府は新東名高速道路を中心とした実証実験を通じて、その効果を検証しています。(※)
結果として、同じ重量を輸送した場合はドライバー数を半分に削減することが確認されました。これを踏まえ、特車通行許可基準を緩和し、ダブル連結トラックの本格的な普及を目指しています。
※出典:国土交通省,ダブル連結トラックについて,p10,p29
安全性の評価
ダブル連結トラックの普及には、道路交通の安全性が重要です。
政府は、実証実験を通じてカーブや急ブレーキ時の挙動を詳細に検証しています。(※)
結果、カーブ区間や急ブレーキ時でもふらつきや横揺れが発生せず、安定した運行が可能であることが確認されました。ダブル連結トラックの安全性が評価されたことも特車通行許可基準の緩和が進んだ一因です。
※出典:国土交通省,「ダブル連結トラック」の本格導入を本日よりスタート,p1
5. まとめ
本記事では、ダブル連結トラックの基本概要、メリット、導入における課題、政府の取り組みについて解説しました。
ダブル連結トラックは、物流業界に革新をもたらします。1台で通常のトラック2台分の荷物を運べるため、輸送効率が飛躍的に向上するとともに、環境負荷の低減や労働環境の改善にも寄与するでしょう。
また、政府の規制緩和や安全性の検証といった取り組みが進んでおり、ダブル連結トラックの導入環境が整備されつつあります。ただし、導入コストや運転者の育成、通行区間の制限といった課題もあるため、これらに対応する具体的な計画が必要です。
物流効率化と環境配慮を両立する手段として、ダブル連結トラックの導入を検討してみてはいかがでしょうか。






